新年度からあっという間にゴールデンウィークを迎え、初夏が顔をのぞかせる季節となりました。
歳を重ねるごとに、時の流れをはやく感じるというのは、「感じられる時間の長さは、年齢と反比例的な関係にある」という「ジャネーの法則」や、身体の代謝の状態が影響しているといわれています。
ともあれ、歳を重ねることで時間の流れをはやく感じるということに異論がある人は、1人もいないのではないでしょうか。
今回は、そんな「時間の流れ」について、いくつかの本を読み、腹落ちした時間は「未来」から「過去」に流れているという考え方について掘り下げていこうと思います。
できる限り、スピリチュアルな話によらないように(笑)、日常的な具体例を示しながら書いていきますので、ぜひ、気楽に読み進めてくださいね。
時間は「未来」から「過去」に流れていると腹落ちした話

まず、1つ質問。
時間は、「過去」から「未来」に流れていると思いますか。
それとも、「未来」から「過去」に流れていると感じるでしょうか?
常識的には、「過去」から「未来」に流れているが大半の答えだと思います。
(もし、すでに「未来」から「過去」に流れていくと感じている場合は、答え合わせの感覚で読み進めてください。)
僕も何も疑うことなくそんな気がしていました。
しかし、メディアアーティストの落合 陽一さんの著書や、高城 剛さんのメルマガ、それ以外にもどこかのメディアでの女性作家(誰だか思い出せず…)の発言で時間は「未来」から「過去」に流れているという話をたびたび目にし、機会があったらその概念についてゆっくり考えてみようと思っていました。
そして、この1か月ほどいくつかの本を読み、自問自答を繰り返した結果、今は時間は「未来」から「過去」に流れていると腹落ちしてしまっています。
なぜか。
まず、具体例を2つ挙げてみましょう。
1年後に退職をすると告げて、転職活動した話
僕は38歳の時、約14年勤めたアパレル企業から、Webマーケティング支援会社に転職しました。
38歳という年齢で、未経験の業種に転職を決めるのは、とても難易度の高いことだと考えていたので、綿密な準備と退路を断つことが必要でした。
そのため、その当時勤めていた企業の上司に「転職を考えています。まだ転職活動を始める前ではありますが、決まっても決まらなくても1年以内には退職させて頂きたいです。」と相談しました。
本題からズレてしまうため詳しい話は割愛しますが、転職先のあてがなく、所属企業と良好な関係性を築いている状態でのこの発言は、なかなかリスクの高い行為です。
しかし、自分の未来を先に決定したことで、その未来に対して、今この瞬間の行動の量と質が変わったのは事実でした。
結果、その相談をした6か月後に、希望していたWebマーケティング支援会社から採用のご連絡を頂きました。
その6か月は、仕事と子育ての合間に、HTML・CSS・JavaScript・PHPといったWebを構成する基本言語を学び、自分でWebサイトを複数つくり、そのサイトへのアクセスをもとにアクセス解析レポートをつくった上で、それをポートフォリオとしました。
具体的な未来を決定したことで、現在がつくられ、それが過ぎ去って経験やキャリアになったのです。
格闘家が試合にむけて減量をする話
僕は、総合格闘技を見るのが大好きです。
総合格闘技やボクシングの試合を観たことがある人ならわかると思いますが、定められた体重をクリアした上で当日の試合が行われます。
格闘家にとって、体重差がある選手との試合ほど難しいことはないようで、試合当日に少しでも相手より大きい状態で試合ができるよう、試合前に急激に体重を落として、当日にリカバリーで体重を戻すのが一般的のようです。
もちろん、当日のコンディションが悪いのはもってのほかなので、体重を急激に落として、急激に戻すのが正という話ではないようですが、前日計量から当日までに、5~10kgくらい戻す選手が多いように思います。
そして、この試合に向けての減量。
まさにこれも時間が「未来」から「過去」に流れる例といえるでしょう。
たとえば、2024年6月9日に試合があるとした場合、約1か月前である今週あたりからゆっくりと減量を始め、1週間前から本格的に落としていく感じでしょうか。
「未来」に行われる試合に向けて、「さて、少しずつ体重を落としていくか。」という想いが「現在」をつくり、その「現在」が一瞬で「過去」になっていく。
もし「未来」の試合がなければ、体重を落としていく行動は「現在」で起こらないでしょう。
「未来」への「想い」が「現在」の行動をつくっているといえるのではないでしょうか。
ここで挙げた例以外にも、「明日は朝早くから山梨に渓流釣りに行くから、今日は22時までに寝よう。」だとか、「ヨガ指導者の資格を1年以内に取りたいから、●●スクールの養成講座を受講しよう。」といった日常的な事例で考えてもらうと、「未来」を想像することで、「現在」のとらえ方と行動が変わってくるのがわかると思います。
「未来」を想像し、その「未来」を実現しようという「想い」が現在の行動となり、「過去」となっていくということです。
これが僕が腹落ちした、「未来」が原因となり「現在」をつくる未来原因論となります。
そもそも時間は存在しない!?

時間というものを少し掘り下げて考えてみましょう。
とは、いっても物理学に対して専門的な知識は一切持ち合わせていないので、著名な物理学者の言葉を借りながら掘り下げてみます。
イタリアの理論物理学者であるカルロ・ロヴェッリ著の『時間は存在しない』では、「この世界に絶対的な時間は存在しない」という考察をしています。
その根拠として、アインシュタインの相対性理論を例にあげ、「宇宙には共通の現在が存在しないため、絶対的な時間も存在せず、時間は人間が生み出した概念である」と述べているのです。
ようは、物理学の視点から考えると「時間は人間が生み出した概念である」ということ。
では、人間はどうやって時間という概念を生み出しているのかという説明として、エントロピー増大の法則が引用されていました。
エントロピー増大の法則とは、物事は放っておくと乱雑・無秩序・複雑な方向に向かい、自発的に元に戻ることはないという法則のこと。
エントロピー増大の法則の例は以下のとおり。
- アツアツのお茶を放置していたら、時間とともに冷め、自発的に再度沸騰することはない
- きれいに整備された野球のグラウンドは、徐々に乱れていくが、自発的にきれいになることはない
- くしゃくしゃに丸められてしわくちゃになった紙が、自発的にきれいでシワのない状態に戻ることはない
人間は、これらの状態の変化を目の当たりにして、時間が存在していると認識しているとのことです。
逆説的にいうと、エントロピーが増大することで、様々なものごとの状態は変化していくが、それが時間が存在することの証明にはならない、ということ。
ようは、時間のとらえ方は人によって異なるものであって、「過去」→「現在」→「未来」の人もいれば、「未来」→「現在」→「過去」の人もいて当然であるということです。
面白いですね。
そして、僕自身の価値観でいえば、「過去」に原因をおく過去原因論ではなく、「未来」に原因をおく未来原因論の方が、しっくり馴染みます。
ちなみに、西欧文化に影響を受ける江戸時代までは、時間は「未来」から「過去」に向かって流れてるという考え方が常識だったようです。
そのため、江戸時代に使われていた、和時計は、今の時計のように針がチクタク左(過去)から右(未来)へ動くものではなく、針が固定され、文字盤が右(未来)から左(過去)へ動くものもあったそうです。
時代によって、時間のとらえる方向が異なるのはとても興味深いですね。
今を生きる
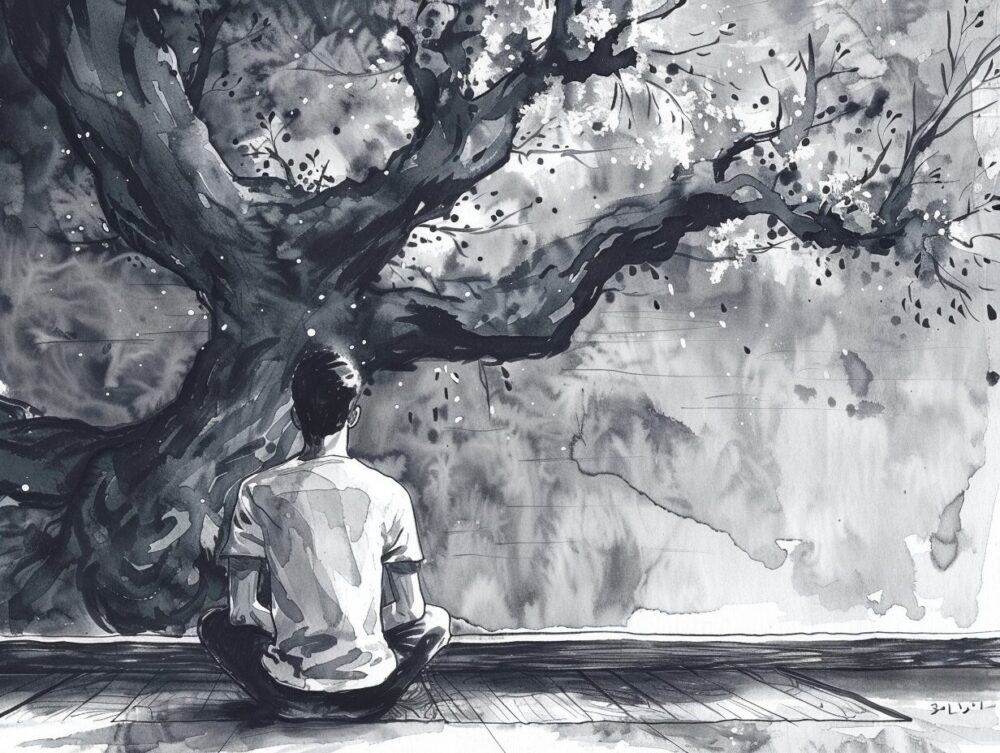
では、結局のところ未来原因論でとらえたところで、何がどう変わるのか。
それは、2つ前の章でも具体例として挙げたとおり、自分が望む未来に向けて「今」をつかむことができることです。
「今」を生きることは、「過去」や「未来」にとらわれない仏教の教えでもあり、1つの真理です。
ちなみに、「今を生きる」という言葉は、英語で「seize the day.(今をしっかりつかめ)」、ラテン語で「carpe diem(その日を摘め)」といいます。
どこにいっても、「今を生きる」という言葉に対する格言がありますが、それくらい時代と国境を越えて、「今を生きる」ということが真理だったのではないでしょうか。
「未来」を想像し、その瞬間を摘め
この「今」をつかむ上で、「過去」の出来事や経験、トラウマをもとに「今」を生きるか。
はたまた、つかみ取りたい「未来」を想像し、その想いをもとに「今」を生きるのか。
どちらが正解という話ではないですが、僕は後者である未来原因論で生きるのが性に合う気がします。
「未来」から流れてくる時間に対して、想いをもち「今」を生き、それが「過去」になる。
これが、僕にとっての本来の時間のあり方です。
今回のこの文章を書くことで、それを言語化することができました。
このコラムが、あなたにとっての「時間」の概念を考える一助になれたら幸いです。
おわりに
今回は、時間は、「未来」から「過去」に流れていることについて、自分なりに掘り下げて書きました。
学生時代は、歴史年表を見ながら左(過去)から右(未来)へ時間軸が進んでいくことを疑いもせず、その価値観をもったまま大人になったような気がします。
ふと立ち止まって、改めて時間について考えてみたことで、自分の中でパラダイムシフト(固定観念を破る感覚)が起こり、とても有意義な時間となりました。
少し先の「未来」を見て、今この瞬間を生きることは、今までの自分にとらわれずに人生を送るヒントのように感じます。
今、目の前のものごとで悩んでいる、そこのあなた。
一度立ち止まって、今この瞬間のとらえ方を見つめ直してみるのもいいかもしれませんね。
では、5月も愉快にやっていきましょう。

