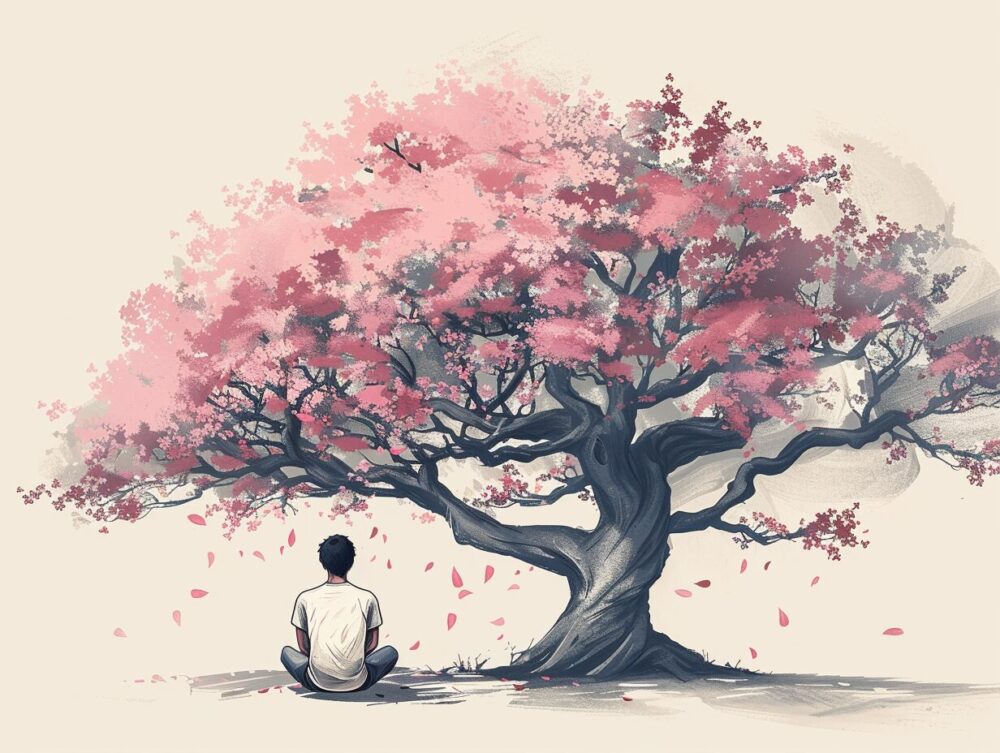別れの季節、3月。
組織に属しているわけではないので、あまり別れを実感できる出来事は起こりませんが、周りを見渡すと新たな領域にチャレンジしている友人がチラホラ。
新たなチャレンジは、始まりは「ツラい…」「不安だ…」がデフォルトですが、時間の経過とともに「挑戦してよかった!」とほぼ思えるものです。
動かずに新しいことをしないことが、未来の自分にとって一番首をしめる行動になっているんだよなぁ、としみじみ思いながら、今タイピングしています。
僕自身の2月のメイントピックは、「瞑想」の習慣化と、広告運用の案件が始まったことです。
「瞑想」は、毎日60分の瞑想を行うようになってから、呼吸への意識、足るを知る感覚、仏教の歴史への興味、週1度のお寺での坐禅など、まんまと沼へとズブズブにはまっています。
8週間のMBSRプログラムを開始したり、「アイスマン」という異名をもつヴィム・ホフさんの呼吸法を取り入れたりと、興味が尽きることはありません。
細かく書いていくと止まらなくなるので、また別の機会で書いていきますね。
広告運用に関しては、Web上の様々なコンテンツのアクセス解析は普段から行っているのですが、実際に広告を運用していく機会を得られたので、「水を得た魚」状態で日々管理画面に触れています。
今回は、そんな新たなことをやりながら日々考えていた「観察する」ことについて、簡単にコラムを書いていこうかと。
毎度のことながらサクサクと書いていきますので、コーヒーブレイクのお供にどうぞ!
観察とは?

冒頭にも書いたように、ここ最近は毎日瞑想をする中で、湧き上がってくる感情や思考を「観察」し、手放し、呼吸に意識を戻すトレーニングを実践しています。
そんな日々の瞑想を通じて、日々多くの情報を「みて」いるんだと再認識している最中です。
起きている間、膨大な情報を「みて」いる僕たちですが、「みる」と一言でいっても「見る」「観る」「視る」「診る」など様々な「みる」が存在します。
その中で、意図的に目を向けて、形や様子を探るというニュアンスがある「観る」行為は、物事の習得や瞑想においても非常に重要な行為です。
そんな「観る」という意味合いが含まれた「観察」という言葉をあらためて辞書で調べてみました。
かん‐さつ〔クワン‐〕【観察】
[名](スル)
1 物事の状態や変化を客観的に注意深く見ること。「動物の生態を—する」「—力」2 《「かんざつ」とも》仏語。智慧によって対象を正しく見極めること。
goo辞書
「客観的に、対象に意識を向けて、注意深くみる。」
これが、「観察する」という言葉の意味になります。
この「観察する」という行為。
「客観的」にみるという事が、実はなかなか難しいことだなぁと思っています。
そもそも人がモノゴトを「観察する」時は、当たり前に主観でモノゴトをみていますよね。
客観的に、固定概念や偏見を捨ててモノゴトを見る機会って、正直ないと思います。(今までの経験や知識からモノゴトを判断するのは人のデフォルトモードです)
知識はとても大事ですが、注意深さを欠く知識は、固定概念や偏見になってしまうものです。
ということは、注意深く、客観性を持ちながら、偏見を捨て、正しくみること。これこそが「観察する」ということになります。
(少し深く掘り下げてしまいましたが、この掘り下げはこの後の展開に必要なので、省略せずに書くこととします)
「観察する」行為をこのように考えていくと、「観察する」って実はけっこう難しくないか?と。
ただ、この「観察する」スキルこそが、この情報が溢れまくった現代において、とても重要なスキルだと思っています。
僕の善は、あの人の悪

「観察する」ことについてここまで書いてきましたが、多くの人が「観察する」後にすることはなんだと思いますか?
10秒で考えてみてください。
(……….)
それは、「判断する」ことです。
モノゴトを目にしたり、感じたりした後、そのモノゴトが何であるか、「判断する」のが人間の習性というもの。
たとえば、芸能人の週刊誌報道をニュースで見た時。その報道について、どちらが善くて、どちらが悪いのか判断していませんか。
別の視点で考えてみましょう。3月のこの時期に『最高気温15℃』と聞いたら、北海道に住んでいる人は「暑そう」と考え、沖縄に住んでいる人は「寒そう」と考えると思います。
これも判断です。
気温15℃という事実に対して、人によって異なる判断を下します。
そして、この「判断」という行為。少々やっかいなんです。
というのも、他人との異なる判断によって、言い争いが起こったり、ストレスを感じたりするのが、この判断のやっかいな特徴です。
判断によって、善悪を自ら決め、価値観の違う声にストレスを感じるのはなんとも不毛な行為だと思いませんか。
「善」の対義語は、「悪」ではなく「もう1つの善」。僕が「悪」だと主張するものは、他人から見たら「善」である可能性もあります。
そんなことで、人と価値観や意見を争っても解決することはまずないでしょう。
であれば、身の回りでおこっている様々な出来事を「判断」するではなく、ただ「観察する」そして「理解する」ことが自分らしく生きていく鍵。
そんな事を「観察する」ことを通じて、あらためて気づいている最近です。
そして、自分に集中していく
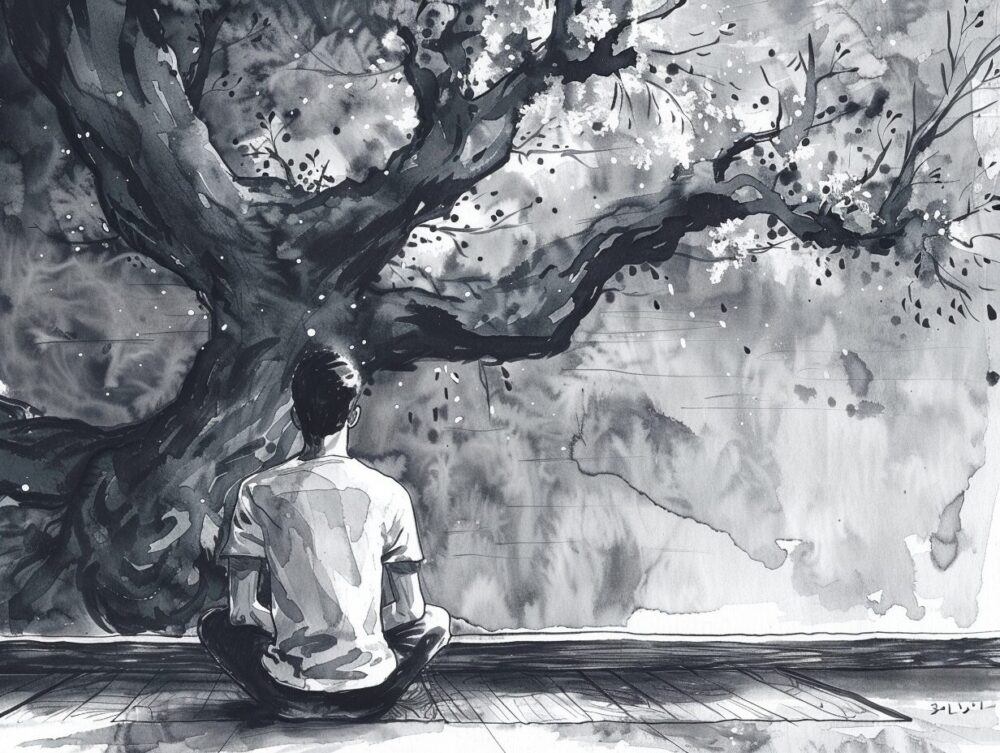
さて、身の回りで起こる出来事を「観察」し「理解」したら、次はどうするか。
それは、「目の前のことに集中する」ことです。
呼吸瞑想では、
→自分の呼吸に意識を向ける
→余計な思考が浮かんで来たら、その思考に気づく
→再び呼吸に意識を向ける
という手順で行うのが一般的です。
ここでの肝は、不要な思考に気づき、すぐに手放して再び呼吸に意識を向けること。
様々な思考が出てくることを否定せずに、それに「気づくスキル」、「手放すスキル」、「再び目の前のことに集中するスキル」を高めていくのが、重要です。
これは、普段の生活にも置き換えられるスキルですよね。
日々、大量にあびる有象無象の情報に、いちいち「これはよくない!」「悲しいな…」「あの人が言っていることは正しい!」「世の中、悪い方向に進んでいる…」などと判断しないこと。
それらのニュースや情報に「気づき」、こういうことが起こっているんだなと「理解」し、そこから意識を自分のやるべきことに戻していく。
そうする事で、無駄に疲弊せず自分に集中して、自分の人生を前に進める事ができます。
瞑想は、こういった気づきを与えてくれる意味でも、自分にとっていいトレーニングになっています。
ぜひ、今一度、自分の人生に集中したい人、足るを知る感覚を取り戻したい人は瞑想を試してみてくださいね。
おわりに
今回は、「観察する」ことについてのコラムを書いてきました。
情報があふれるこの時代に、自分自身に集中していく難易度は、かなり上がっています。
それを攻略する鍵として「観察する」「手放す」「再び自分に集中していく」という手順をオススメしてきました。
3月も引き続き、日々の瞑想を実践しながら、自分の内側と向き合う日々を過ごしていきます。(仕事もしっかりやります(笑))
定期的に、いくつかのお寺で開催されている坐禅会にも参加していますので、興味のある人はぜひご一緒しましょう。
お寺さんに伺うだけでも日常の喧騒から離れられるのでオススメです。
では、また。